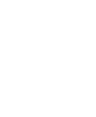
地上に太陽を~日本で進む核融合研究~
核融合

エネルギー

原子力研究
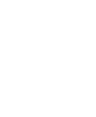
核融合

エネルギー

原子力研究
核融合(英語ではニュークレアフュージョン)は、太陽のエネルギー源として見いだされ、未来のエネルギー源としての利用のための研究開発が60年以上に渡って世界中で続けられています。他の科学技術とは異なり、日本は早い段階から世界の核融合研究開発を牽引してきました。2020年代に入って、核融合の研究開発に大きな転換期を迎えています。ここでは、核融合の基本原理から日本での研究活動の最前線までを簡単に解説します。
世の中の全ての物質は、固有の分子(あるいはさらに小さい原子)から形作られています。身の回りのエネルギー源としてよく知られる「燃焼」は、おもに空気や酸素を酸化剤とし、燃料(可燃物)分子を激しく酸化して、もとの物質とは異なる物質を生成する反応です。例えば、1モルの水素ガスは燃焼により286キロジュールの熱と1モルの水を生み出します。1モルの水素にはおよそ1兆×1兆個もの水素分子が含まれているため、水素の燃焼の1反応当たりの反応熱は3.8x10の-19乗ジュールになります。
原子は、ほとんどの質量を占める原子核と、その周りに分布する少数の極めて軽い電子から構成されています。化学反応では、原子核はそのままで、電子の配置が変化し原子の電気的な結合の状態が変化するだけです。水素の例のように反応後に生まれる分子などでの原子の結合がより強固になる場合、この結合エネルギーの増加分が反応熱として取り出されます。
原子核は大きさが原子全体のおよそ10万分の1で、陽子と中性子(合わせて核子と言います)の複合体です。全体として正の電荷を持ちますので、原子核そのものが反応する核反応が起こるためには、原子核と電子が分離して、お互いに高速で運動する超高温のプラズマ状態になければなりません。
私たちの太陽は典型的な恒星で、中心部は1500万度の超高密度プラズマ状態になっています。4つの軽水素原子核(陽子p)が何段階かの反応を経て1つのヘリウム4原子核に代わり、1反応当たり11.92メガ電子ボルト、すなわち、1.9x10の-12乗ジュールの反応熱が生み出されています。この反応は、pp反応と呼ばれます。この反応熱は、先の水素の燃焼に比べて、10の7乗倍すなわち1000万倍の量になります。この違いは原子核の中の核子の結合エネルギーが、分子中の原子の結合エネルギーに比べて桁違いに強いことによります。
pp反応の第一段階では、2つの陽子のひとつが中性子に変換され、重水素原子核dが作られますが、この反応は極めて遅く(専門的には「弱い力」で進行するため)、太陽が何十億年も熱や光を供給する理由となっています。しかし、そのために単位体積あたりのエネルギー発生率は極めて小さく、人体が平熱を保つのに必要なエネルギー生成密度と同程度かそれ以下です。したがって、ある程度の出力のエネルギー源とするには、膨大な体積が必要となることを意味します。強力な重力による高密度のプラズマ閉じ込めの実現とあわせて、この事実は人間が太陽の核融合反応をそのまま地上で真似することを困難にしています。
水素には、原子核内の中性子数の違う仲間(同位体、英語ではアイソトープ)が存在します。重水素の原子核dと三重水素の原子核tを燃料とする核融合反応(DT反応と呼ばれます)は、水爆で初めて実証されました。これを「制御された」条件で持続的に行うための研究が、第二次世界大戦後に、まず軍事研究として開始されました。しかし、10年足らずのうちにほとんどの研究成果が公開されました。これは、太陽の中心部並みのプラズマ状態を、膨大な質量に基づく重力なしに制御することの困難さが共通認識となったためでした。当時、ある高明な科学者は、この状況について「私達は、出口の無い煉獄(れんごく)の中にいる」と述べていました。この頃から日本でも制御核融合の研究が始まり、何人かの日本人がこの煉獄からの脱出に寄与することになりました。
なお、重力の代わりに磁力を用いてプラズマを制御する場合、電磁石の技術的な制限から、10気圧程度のプラズマしか閉じ込められません。DT反応が起こる温度は太陽中心より1桁高い1億度ですが、密度は、1気圧の空気の1万分の1程度の「真空」状態とかわりません。したがって、仮に1000MW級の核融合炉が炉心損傷を受けても、水爆のような核爆発が起こることは全くあり得ません。
燃料の重水素は、普通の水中に6000個の軽水素に1個の割合で含まれるため、ほとんど無尽蔵です。三重水素はトリチウムという名前で、原子力発電所からも放出されている事が知られていますが、高層大気中で、宇宙線との核反応で生成され、同じ量が自然に崩壊して失われています。従って、原子炉が作られる前から、地球全体では一定量のトリチウムが天然に存在していました。ごく微量ですが食物に取り込まれ、私たちの体の中にもごくわずかに存在しています。当然ながら、これによる体内被ばくも検討されていますが、他の天然放射性物質からの体内被ばくに比べて無視できるレベルです。核融合炉の燃料として必要な三重水素の量は膨大ですので、リチウム(特に存在比が10%のリチウム6)に、DT反応で生まれる中性子を当てて自己生産することが想定されています。起動時の三重水素は、原子炉などから提供することも検討されています。
リチウムの埋蔵量はウランや石油よりずっと豊富です。また、DT反応や、付随して起こるDD反応では動力用原子炉で問題となる長寿命の高レベル廃棄物は生まれません。
核融合研究は早い段階で国際的な情報交換が進みました。その最も大きな舞台がIAEAが主催する核融合エネルギー国際会議です。1961年にザルツブルクで第1回が開催されてから、およそ2年ごとに、世界各国が派遣した研究者が情報交換を続けて、2021年5月に第28回がオンライン開催されています。現在、主流となっているトカマク装置を旧ソ連の研究者が提案し、英国を中心とする国際チームがその性能を新開発のレーザー装置で検証した成果もこの会議で報告されました。
1990年代にこのトカマク装置で臨界プラズマ状態を実現する見込みがたち、米ソ首脳会談を契機にITER計画がスタートしました。ITERは、ラテン語で「道」を意味し、核融合炉への道をひらく世界最大のトカマク装置です。2025年の完成を目指し、南仏で国際協力で建設が進められています。ITERを建設しているITER機構において、日本は機構長あるいは副機構長のポストに人材を供給するなどして、中心的な役割を担っています。また、定期的にITER機構の研究者や技術職員の国際公募が行われています。
QSTの前身機関であった日本原子力研究所は、旧ソ連のトカマク装置の概念をいち早く取り入れ、以来、日本のみならず世界の核融合研究をリードしてきました。燃料粒子の制御のためのダイバータ、巨大な炉心プラズマの中心まで届く、負イオン源を使った加熱用ビームシステム、自発的なプラズマ電流駆動メカニズム、磁力線のねじり制御によるプラズマ内の断熱層などがここで生み出され、ITERを始めとする各国の核融合装置に取り入れられています。
2020年3月、QSTは新しいトカマク装置JT60-SAの組立を完了し、試運転前の最終総合試験を行っています。数字の60はベースとなった古いトカマクの真空容器の体積が60立方メートルであったことからきていますが、この新装置では体積の値はおよそ2倍で、ITERが完成するまでは世界最大のトカマク装置となっています。JT60-SAは装置建造の技術開発、炉心プラズマ研究の革新の他に、実用炉の設計段階で使用される様々なシミュレーションコードの性能検証のための実験データの提供などが期待されています。
提供
大阪府立大学 放射線研究センター
松浦 寬人 教授
URL:http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/~matsu/